富士山で、まさかの“1週間で2度”救助されるという前代未聞の出来事が起きました。救助されたのは、東京・渋谷区に住む27歳の中国籍の男子大学生。彼はまず4月22日、富士山の山頂付近で高山病を発症し、自らの通報によって山梨県の防災ヘリで救助されました。ところが、それからわずか4日後の26日、彼は再び富士山へと足を踏み入れます。目的は、前回の救助時に山頂付近に置き忘れた携帯電話などの荷物の回収。ですが、またしても体調を崩し、今度は別の登山者によって8合目付近で倒れているところを発見され、静岡県警の山岳救助隊により、雪の残る険しい山道を約7時間かけて担架で5合目まで搬送されました。命に別状はなかったものの、この無謀な登山が国内外で大きな波紋を呼んでいます。
特に今回問題となったのは、登山が富士山の閉山期間中だったという点。登山道は封鎖され、山小屋やトイレ、救護所もすべて閉鎖されている中で、単独行動を取ったことで、救助の難易度とリスクが大きく高まりました。気温は氷点下にまで下がり、道は雪や氷で覆われ、救助隊でさえ移動に苦労する厳しい環境。そんな中で2度も救助を要請した彼の行動には、SNS上でも「愚かすぎる」「罰金を徴収すべき」「救助隊に迷惑をかけるな」といった厳しい声が多く寄せられました。日本国内にとどまらず、中国国内のネット上でも批判の声が殺到しています。
登山家の野口健さんも自身のSNSで「救助費用を請求するべき」とコメントし、山に登るならば山岳保険の加入や安全意識が不可欠であることを強調しています。実際、富士山では近年の登山者増加による安全対策の一環として、入山料や登山者数の制限などが設けられるようになっていますが、今回のように閉山中の登山を完全に防ぐ仕組みはまだ整っていません。
なお、この大学生は2度目の救助の際、警察に対して「もう二度と登らない」と語ったとのことです。ゴールデンウィークで登山を計画している方も多いかもしれませんが、富士山の登山道は現在封鎖されており、救助体制も整っていない状況。登山は開山期間中に計画的かつ安全に行うことが、何よりも大切です。今回の一件を教訓に、自然を軽視せず、万全な準備と知識を持って向き合う姿勢が求められています。
海外の反応
🧑 一度でも恥だ。二度目なんて、恥の上塗りだぞ。
👨💼 本気で笑わせてもらったよ。見事なやり口だ。
👨🏫 遂にダーウィンがこいつに審判を下すだろう。
🧑 携帯、取り戻せたのか?
🙍🏾♂️ 信じられないかもしれないけど、俺もジェットスキーで海に取り残されて沿岸警備隊に救助されたんだ。翌日戻ったらまた取り残されて、砂浜を這って海に戻ったさ。
👱♀️ 彼、救助されるのが好きなんじゃないかな。
👨💼 横須賀に駐屯してた俺は富士山に登る予定だったが、前夜に友人と飲んで寝過ごした。23歳の頃は登れたけど、43じゃもう無理だな。
👩💼 あれ、彼にいくら請求されるんだろうか?
👩 一度目の教訓は生かせなかったの?救助隊の人たちの気持ちを想像してみて…「またお前か!?」ってね。
🙍🏿♂️ 三度目の正直だな。
👱♂️ 電話はかけたくても…ああ、でも…。
👨 富士山は標高は大したことないけど(高山病…はは)、天候はひどいことがある。7月でも頂上は凍って風は強い。
👩 ユタのハイカーのようだね!砂漠で装備も水もなしに摂氏約40度の中をハイキングするなんて。
👱♂️ 救助ありがとう…あ、やべ、携帯忘れた。
👨 運良く別の登山者がいてくれたから助かったけど、状況が違ってたらどうなってたか。
👩 その携帯には何が入ってるんだ…👀👀
👨 日本の親切とやる気精神が命を救ったんだろうね。母国チリならミイラ祭りだよ。
🧑 新しい携帯を買えばいいだけだろ。
🧑 自然淘汰に任せればいいのに!?
👨 あいつの携帯調べろよ。何か隠してるに違いない。
👨 7月と8月が登山シーズンなのに、なんて馬鹿なんだ。
👱♂️ 唇のグロスを取りに三度目の挑戦か。
👨💼 二度目の救助は自己負担だな。
👨💼 恐らく全ての救助費用を請求されるだろう。
🐰 いい奴らだな。
👨 請求書は彼に来るだろうよ。日本にたかってばかりはいられない。
🧑 最初は大目に見ても、二度目は10倍請求してやれば賢くなるかもね。
👩 すべての救助費用と常識の欠如に対して彼は支払うべきだわ。
👩 愚かだわ。
👨 標高3,000メートルで高山病?どんだけ不調なんだよ。アフガニスタンなら座ったまま暮らしても平気だぞ。
👩 ああ、もう何も言うまい、この阿呆に。
👨 日本に住んで何度も富士を登った経験から言うと、誰でも登れる。問題は高齢の登山者が道を塞ぐことだ。
コメントは以上になります。
海外の反応を通して見えてくるのは、登山者個人の判断ミスに対する厳しい視線と、公共資源を使っての再救助に対する不満の声です。
一部には冗談交じりのコメントもありましたが、全体としては「自己責任」と「公共負担」の線引きについて、多くの人が強い関心を抱いていることが伺えます。
登山という行為のリスクや準備不足の代償について、国や文化を越えて疑問が共有されたかたちでした。

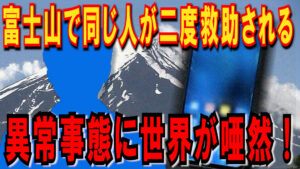


コメント